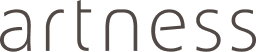上出惠悟 × 高山健太郎 後編|「“間”にある無限の可能性を見つめる」
ARTIST INTERVIEW
artness代表の高山健太郎が気になるアーティストやキュレーター、研究者などをお招きし、「アートと〇〇の間」を主題に、21世紀の時代に求められるアートの役割や、新たな可能性を探るウェブマガジン。第1回は「上出長右衛門窯」の六代目であり、合同会社上出瓷藝の代表として他業種とのコラボレーションやデザイン制作を展開、また一人のアーティストとして作家活動を行う上出惠悟さんと「アートと工芸の間」をテーマに対談。前半では過去に手掛けた共同プロジェクトについて振り返りましたが、後半はメインテーマである「アートと工芸の間」についてお届けします。
ー工芸やアートの「間」を自由に漂う上出さんと考える、アートの新たな可能性。
高山 上出さんの仕事ぶりを拝見していると、アートの文脈で活動をしているときもあれば、家業の九谷焼にアートを取り入れた活動をしているときもあり、一般的には「アートか工芸か」みたいな二元論で語られがちなのですが、実はその間に色んな可能性があるんだということを示してくれているように感じています。「甘蕉」についても、上出さんにとっては作家・上出惠悟のアートワークとして取り組んでいらっしゃると思いますが、ベースになっているのは九谷焼の技術です。一方で「寿福老」はパブリックアートのように橋場町の顔になっていますが、上出さんとしては作家ではなくアートディレクターの立場で上出長右衛門窯が手がけたお仕事ですが、改めてその幅の広さがすごく面白いなと思います。

高山 アートと工芸といった枠組みは常に意識していらっしゃるのでしょうか?上出さんは多様な引き出しを持っていて、そのなかから様々なエッセンスを取り出してミックスしアウトプットすることがとても上手だなと思っていて、受け取り方によって色々な解釈ができるところがユニークですよね。
上出 うーん。色んなケースがあるので難しいのですが、僕のなかに「常に新鮮なものを作りたい」という気持ちはあります。ひとつ思い出したのは、僕が卒業制作で「甘蕉」を作っていたときが一番「間」について考えていて、工芸と現代美術の間を攻めようというか、その「間」って一体どこにあるんだろう?って思っていたんです。卒業制作を森美術館元館長の南條史生さんが「ホワイトキューブに置けばたちまちアートになるし、工芸のお店に置けばたちまち工芸品になってしまう」と講評してくれたのですが、その不安定さを逆手に取ると実に面白いものだと感じていました。その後もずっと伝統工芸とデザインの間とか様々な垣根に興味があって、問題提起というほどではないけれどアプローチをしていました。ただ、以前は境界みたいなものをすごく意識していたんですけど、今はあんまりそこを攻めようというか、狙って何かやろうみたいなことはそれほど思わなくなりました。今は工芸側からのアプローチもかなり増えているので、幅は色々と広がっているように思います。
ー枠組みや技法に縛られない、ピュアな表現への憧れ。
上出 中国・江西省に景徳鎮市という焼き物の有名な産地があるのですが、昔は官窯として国から管理されていたので、職人たちが自分の思うように自由に作品を作れなかったり、絵柄に関しても様式が細かく決められていて、龍の爪の数まで指定されていました。それから国の力がどんどん弱くなっていき、抑圧から解放された反動として職人たちが自由に絵を描く「古染付」と呼ばれるものが出てきました。長右衛門窯はその古染付にすごく大きな影響を受けているのですが、当時のものを見ると非常にゆるくて。なんだか素材も悪いし、絵柄も裸の人が踊っているような絵があったりすごく自由闊達で、線も別に上手って言えないような子どもが描いたような絵がたくさんあって、でも、それがすごく面白いなって思っています。

上出 工芸が改めて注目されていますが「技術」というものがそこまで必要かなというか。例えば九谷焼は国から「伝統的工芸品」に指定されていますが、その枠組みにこだわることによって、思考が停止してしまうことが起きている気がします。硬直化が起きて行き詰まり、技術はあるのに何をしたら良いのか分からなくなってしまったりしているように見える。寿福老もそうなのですが、僕はもっと根源的な、ピュアなところにすごく興味があるんです。もちろん技術は必要だし、磨かれていくべきとは思いますが、もうちょっと「器用な人」って感じで何でもやったらいいんじゃないかなって思う。壁みたいなものを作らずに、間に立ったり、行き来することで新鮮さや楽しさを持ち帰ることがいいと思います。
高山 例えばあの世とこの世を隔てるといわれている三途の川や、神社であれば俗世と神の領域とを分ける鳥居がありますよね。一般的には生か死なので「間」はないはずなのですが、そういう中間の領域を作るというのは日本人的なクリエイティビティだと思っています。お話を伺いながら、上出さんは美術を学ばれたり家業として工芸に携わったりしていて両方が見えているからこそ、その「間」について考えることができるのではないかと思いました。
ー徹底的に「今」と向き合う上出さんが見据える、少し先の未来のこと。

高山 上出さんは今年、40歳という一つの節目を迎えられるわけですが、これから先、九谷焼の未来というものをどのように見ているのでしょうか。また今後の上出右衛門窯の展開などもお聞きしたいです。
上出 そもそも僕はそんなに未来を考えるのが得意ではなくて、常に過去を見ているんです。今後どうしていきたいかというのはほとんど考えていなくて、その時々で自分にとって新鮮なことをやりたいっていう、それ以上の言葉がなかなか見つからないのが正直なところです。ただ、上出長右衛門窯では毎年干支をモチーフにした作品を発表しているのですが、翌年の干支のデザインを考えることは僕にとって未来を考えることなのかもしれないと思い始めました。最近の試みとして、毎月9の付く日に9日間だけオープンするオンラインショップ「9days Shop」を立ち上げて、ここで販売する商品の魅力をインスタライブで伝えています。商品について語るのは僕自身とても勉強になるし、インスタライブはお客さんとのすごく密なコミュニケーションだと思っていて、いま僕にとっては重要な場所になっています。もう一つ、今年(2021年)から商品開発の過程にあるさまざまなアイディアや紆余曲折を文章で配信する有料メディア「上出長右衛門窯の道行(みちゆき)」を始めたのですが、リアルタイムでものづくりの現場を知ることができるのはお客さんにとっても初めての経験なんじゃないかなと思っていて、その反応が今後どのように広がっていくか楽しみですね。

上出 今後やってみたいこととして一つ考えているのは、例えば海外の多くのファッションブランドでは定期的にデザイナーやディレクターが交代したりと新陳代謝によって成長を続けていますが、そういうことって日本の工芸も学ばなきゃいけないと思っているんです。長右衛門窯も僕がずっと引っ張っていくわけじゃなくて、有田のある窯でディレクターをしていた人が長右衛門窯で新しいことをやったり、僕が有田に行って伝統を学びながら窯の新しい魅力を引き出したりするみたいな、そういうことができたら面白いなと思っています。
ー何かと何かがぶつかり合ったときのエネルギーが、新しいものを創造する。

高山 すごく良いですね。産地の抱える問題や伝統工芸に携わっている人たちの悩みを解決する、ひとつの方法になり得るのではないでしょうか。
上出 そうそう。それは必ずしも焼き物という業界内で行う必要はなくて、漆や加賀友禅をしていた人が九谷焼に来たり、九谷焼を作っている人がガラスや金工に行ったりすることで、すごいミックスが起きるのってめちゃくちゃ面白いと思うんです。だから僕、高知の「よさこい祭」と北海道の「ソーラン節」がミックスされることによって生まれた「YOSAKOIソーラン祭り」って、概念としてめっちゃくちゃ面白いと思っています。これが100年くらい続くと、立派な文化になっていくと思うんですよね。異なるカルチャーがぶつかり合ったときのエネルギーによって、何か新しいものが創造されるっていうことは絶対にあると思っていて、家業を百年以上続けるとか技術を伝承するという価値観もすごく大事だとは思うんですけど、全く別のジャンルを積極的に取り入ることによって価値観がリフレッシュされて、新たな可能性を見出せるものが生まれる気がしていて。それが発展することにつながるんじゃないかなって思うんです。そういうことを高山さんのような仕事をしている人が積極的に仕掛けていくと、すごく面白い未来が待ってるんじゃないかな。
ーコロナ禍で浮かび上がった、アートが持つ身体性。

高山 個人の作家として、今やりたいことはなんですか?
上出 油絵を描きたいっていうのはずーっと思っています。焼き物は作業が多くて、特に九谷焼は完成を予想して焼き上がりをコントロールしていく世界だと思っています。しかし絵って不思議で、そこに自分を投影するというか、自分の身体性とかエモーショナルなものとの距離がずっと近くて面白い緊張感があるんです。
高山 なるほど。家業として携わる工芸は制約がいろいろとあるからこそ、個人の作家としては、その制約の外側で制作をしたいということですね。
上出 それと新型コロナウイルスの影響というのはやっぱりあって、コロナの存在を無視できないというか、この時代を無かったことにして次のビジョンを描くことはできないと思っているんです。この間、すごく身体性を失ってたと思っていて、みんなもきっとそう思っているから、山を登ったりキャンプやハイキングをしたりしているんじゃないのかな。僕もすごく頭だけで考えてしまっていたり、ミーティングもオンラインでできちゃうので、身体を動かす機会もどんどん減ってしまったりして。そんななかで、どうしても自分の身体と向き合うことが失われていって、意外とそういうものが大事だったんだなあということに気がついたのがこの2年間でした。

高山 コロナ禍で上出さんは日々の生活を改めて見つめ直し、日常のなかで九谷焼やアートとの接点を模索しているようにも感じます。
上出 近所を歩いたりとか、そのなかで見つけた植物の芽吹きとか、今まで無視してしまっていた小さな存在、それは決して小さいものではないんだけど、道端の人知れず行われてきた営みみたいなことに目が行くようになって。コロナウイルスっていうものが自分たちに与えた影響っていうのはすごく大きいなと改めて思いました。去年の個展では木材をひたすら削ったり組み立てたりとかして必死で身体性を取り戻そうと作品を作っていたんですけど、結構肉体的に疲れちゃって、そんななかで向き合えるものが油絵なんじゃないかなと思っています。

高山 アート作品の良さはやはり生の体験をしたり、その体験を色々な人と共有したりすることができるところで、そういう意味では身体性が高いとも言えるのかなと思います。上出さんがおっしゃるようにコロナ禍でそれぞれが身体との向き合い方も変わってきたなかで、上出さんの油絵をリアルで鑑賞する企画も面白そうです。今後、そういう機会を作れたらいいなと思います。
上出 ぜひよろしくお願いします!

(取材日/2021年10月9日)
LOCATION/kakurezato coffee(kanazawa, Ishikawa)
PHOTO/MASAHIRO TERADA(MARC AND PORTER PHOTOGRAPHY)
TEXT・EDIT/Nana Inoue(umahitosha)