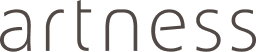上出惠悟 × 高山健太郎 前編|「アートと“工芸”の間」
ARTIST INTERVIEW
artness代表の高山健太郎が気になるアーティストやキュレーター、研究者などをお招きし、「アートと〇〇の間」を主題に、21世紀の時代に求められるアートの役割や、新たな可能性を探るウェブマガジン。第1回は石川県の伝統工芸・九谷焼の老舗窯元「上出長右衛門窯」の六代目であり、合同会社上出瓷藝の代表として他業種とのコラボレーションやデザイン制作を展開、また一人のアーティストとして作家活動を行う上出惠悟さんと「アートと工芸の間」をテーマに対談。アートと工芸のボーダーや、個人の作家と窯の代表という立場のボーダーを自由に行き来する上出さんと共に、様々な間(あいだ)を見つめました。記事は2回に分け、前半は過去に手掛けた共同プロジェクトについて、後半はメインテーマである「アートと工芸の間」についてお届けします。
上出惠悟さんプロフィール
1981年石川県生まれ、2006年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。同年より、1879(明治12)年創業の九谷焼窯元である上出長右衛門窯の後継者として、職人と共に多くの企画や作品の発表、デザインに携わる。2013年、合同会社上出瓷藝(かみでしげい)設立を機に本格的に窯の経営に従事。東洋から始まった磁器の歴史を舞台に普遍的で瑞々しい表現を目指すと共に、伝統や枠に囚われない柔軟な発想で九谷焼を現代に伝えている。主な仕事として、伝統柄をアレンジした「笛吹」や、スペイン人デザイナーを招聘した「JAIME HAYON×KUTANI CHOEMON」シリーズ、九谷焼の転写技術を活かした「KUTANI SEAL」など。最近ではロックバンド・サカナクションとのコラボレーションや、小説家・小川洋子のエッセイ集の装画が話題となった。また個人としても磁器を素材に作品を制作し、精力的に個展を開催している。
― 2人の出会いは2015年。北陸新幹線開業で金沢の街並みが急速に変わりゆくなか進められた、あるホテルの建設プロジェクトがきっかけ。
高山 リノベーション事業を行う株式会社リビタさんが初の試みとしてホテル「HATCHi 金沢-THE SHARE HOTELS-(以下、HATCHi 金沢)」(※)を開業するにあたり、「北陸ツーリズムの発地」というコンセプトを策定する段階からアートディレクターとして携わることになったのですが、上出さんとの出会いは館内に設置する九谷焼の照明や、オープンを記念したオープニング展覧会への出品を相談したことがきっかけでしたね。
(※)「HATCHi 金沢-THE SHARE HOTELS-」/もともと仏壇仏具店だった昭和41年築の中古ビルをコンバージョン・リノベーションして再生された、「北陸ツーリズムの発地」がコンセプトのシェア型複合ホテル。
上出 そうそう、覚えていますよ。
高山 北陸新幹線が開業するまで、金沢にアートを見に来る人はピンポイントで金沢21世紀美術館を訪れるだけで、美術館の鑑賞後に金沢や近隣のアートに触れる機会はほとんどありませんでした。なのでHATCHi 金沢の相談をいただいたときに、「地域のアートを知りたい」と思っている方の欲求に応えたり、石川を拠点に活躍する若いアーティストの活動を知っていただいたり、また交流が生まれたりするようなコンテンツを作ることができればと考えました。上出さんは僕と年齢が近いということもあったのですが、伝統工芸という地域に根ざした仕事をしている一方で外の世界もよく見ていて、ちょうど観光とローカルの、旅人と地元の人との橋渡しをするような、そんなことを一緒にできるんじゃないかと思ったんです。当初、HATCHi 金沢のプロジェクトを聞いたときにはどう思われましたか?
上出 今までにないコンセプトで素敵だと思いました。HATCHi 金沢がターゲットとしたのは若い層でしたよね。もともと僕たちが九谷焼を販売してきたのは高級旅館やホテルに宿泊する高所得者の方々だったのですが、一方で伝統工芸を次の世代につなげていくためには若い人たちへのアプローチが必要だという問題意識を持って、早くから取り組んできました。HATCHi 金沢は一階に宿泊客以外も利用できるカフェがあったり、そこでイベントが開催できたり、良い場所ができるなと思ってすごく可能性を感じていました。
― HATCHi 金沢のエントランス前に置かれた高さ80cmの「寿福老(ことぶくろう)」は、ホテルのシンボルとして多くの人に親しまれ、ホテルが立地する橋場町のランドマークになっている。

高山 HATCHi 金沢のオープン一周年企画では「大寿福老」を手がけていただきましたが、改めてどのような経緯で誕生したのかお話しいただけますか?
上出 もともと僕は普遍的なものを作りたいという気持ちがあって、上出長右衛門窯では「時代を経ても瑞々しさを感じられる九谷焼の焼造」というステートメントを掲げています。なので流行を過敏に追うことはあまりしないようにしていて、商品制作や伝え方などから時代の空気感というものは滲み出てくると思いますが、何十年と月日を重ねても身近に感じられる、ノスタルジーをあまり感じさせないものをなるべく作りたいと思いながら仕事をしています。うちの窯に「笛吹」という絵柄があるのですが、これは60年以上ずっと作り続けている定番商品で、それってやっぱり、その時代時代で人々に寄り添うことができたから、これだけ長く同じ商品を作り続けてこれたんだと思っているんです。そういうものを僕の代でも作りたいというのが命題としてあって、そんななかで誕生したのが「寿福老」でした。HATCHi 金沢から依頼を受けたときに「寿福老」は街のシンボルになり得るすごく重要なものだと思って、ホテルに宿泊する人もそうですが、通りすがりの人にも可愛がってもらえるようなものを目指しました。僕のことを知らない人でも、昔からそこにあったもののように「寿福老」と一緒に記念撮影してもらったり、足元にお金が積まれたりしてお地蔵さんみたいに親しまれている様子を見たりして笑、すごく嬉しかったです。

高山 僕がもともと上出さんに対して抱いていた印象は、金沢21世紀美術館に個人の作家として「甘蕉(かんしょう:バナナ)」が収蔵されているように、あまり上出長右衛門窯や九谷焼というイメージはありませんでした。HATCHi 金沢のプロジェクトで生まれた「寿福老」は、家業として代々守ってこられたことと上出さんの個人の作家としての仕事の、ちょうど中間に生まれたように感じました。作品自体が大きいということもありますが、街のシンボルになり得る存在感がありますよね。九谷焼であれほど大きいものを作るのは難しかったのではないでしょうか。
上出 そうですね。うちの窯はずっと割烹食器が専門で花瓶とか壺とかも作って来なかったので、大きいものを作るノウハウがなくて。依頼をいただいたときに結構大変そうだなと思いました。でも、ちょうどその頃に出会った年配のろくろ師が「もう仕事もないから焼き鳥屋でもしようと思ってる」って言うから、どんなものが得意なのか聞いたら「大きいものばっかり作ってきた」って。それで焼き鳥屋になる前に猶予をもらって、「寿福老」の制作をお願いしたんです。
高山 すごい偶然の出会いですね。上出さんご自身は、大きい作品や自分たちがこれまで手がけたことがない新たな領域への興味はあったのでしょうか?
上出 僕はテーブルに乗るような大きさのものしか作ってこなくて、より大きなものを作れるようになれば可能性も広がるので、やってみたいという気持ちは個人の作家としても窯の経営者としても持っていました。なので「寿福老」は本当に良い機会で、めちゃくちゃ試行錯誤しましたし、何回やっても上手に焼けなくて窯の中で割れてしまうことが何度もあり想像以上に苦労しましたが、この仕事がきっかけで色んなノウハウを学びましたし、うちの職人もまた少し腕を上げることができました。

高山 寿福老にはたくさんのストーリーが内包されているのですね。観光で金沢を訪れた人が「寿福老」と出会い、それがきっかけで九谷焼に興味を持ってくれたり、上出長右衛門窯を知って実際に能美市にある窯を訪れてくれたりしたら素敵ですね。私は観光というものを高解像度で見たときに、人と人とのつながりというものがキーワードになると考えていて、それを「寿福老」が体現しているように感じています。
― アートと工芸の「間」にあり、上出さんと家業をつないだ「甘蕉(かんしょう:バナナ)」。

高山 上出長右衛門窯の仕事とは別に、上出さんは個人の作家としてバナナをモチーフとした作品を継続して手がけていらっしゃいますよね。突然ですが「甘蕉」は上出さんにとってどのような存在なのでしょうか?
上出 実はあまり言語化できてなくて、僕と窯をつなげてくれたものではあるのですが、今だに「いったい何なんだろう?」って思いながら作ってるみたいなところがあります笑。初めて「甘蕉」を作ったのは大学の卒業制作だったのですが、自分の表現というものを考えるにあたり改めて自分の出自が気になって、今まで家族が上出長右衛門窯でやってきた仕事をちゃんと知りたいと思ったんです。そこから僕はものが持つ価値というものに傾倒していったというか、「もの」に対してすごく感動していくようになりました。日本美術や工芸は、説明なしに“すごい”と思えるというか、言葉には表せないところで感動する、何かが宿っている気がしたんです。工芸は素材ありきなので、まず素材があってそれで何を表現するかという考え方なのですが、僕が磁土という素材を使って何が作れるかなと考えたときに、技術がないという。工芸ってイコール技術と言っていいくらい技術が重視されているのですが、高度な技術がない僕でも作れて、かつ自分が九谷焼というものを見た時に感じた素材感をピュアに作品にしたらテーブルの上のバナナになったんです。
ー素材や技法という制約があるからこそ生まれる新たな表現。

上出 油画科の学生だった当時の僕にとって、とにかく磁器という素材を使って何かを作ってみるということが重要でした。焼き終えて窯から出てきたものは、なんだか本物のバナナっぽくて妙にリアルでした。僕がすごく頑張ってリアルに仕上げようとしたわけじゃなくて、焼成することで自然にリアルになるっていうのが面白くって、窯のマジックがすごく効いているなあと思って。だけど完成したものが一体何なのか、工芸なのか美術なのか、はたまたクラフトと呼ばれるようなものなのか、自分自身としてもあまり見たことがないものができたので、これが一体何なのかっていうのが分からなかったけど、卒業制作で展示することでなんとなく着地した感じでした。
高山 今のお話を聞いて面白いなと思ったのが、通常、現代アートをしている人であれば、バナナというコンセプトを決めて絵画で描いたり彫刻で作ったりすることはあると思うのですが、上出さんが生み出したあの質感は、家業の現場を見て学び、磁器の質感や表情に気付いて作品化しているわけですよね。コンセプトありきで作っていくと全く違うものになったのかも知れません。身体を起点としているからこそあの質感が生まれたということ、さらに現代アートの作品として存在していることが面白いと思います。工芸的な思考で作品ができているのですが、実用的な用途ではなくコンセプチュアルな形という、矛盾が内在しているところが面白いですね。

上出 そう、だから上手く言葉にできないんですけど…。僕は「甘蕉」というものを俳句のようなものとして捉えていて。俳句って、五七五という制約のなかでどれだけ新鮮な表現ができるか、面白い表現ができるかということを何百年以上も続けていますよね。僕も定期的に甘蕉を作り続けているんですけど、モチーフや素材や技法という制約があるなかで、その都度新しいことをやってみたり遊びとして面白いことを取り入れてみたりしています。ただ同じものをずっと作り続けるんじゃなくて、そういう風に実験しながら楽しんでいけたらいいなって思っています。
高山 「HYATT CENTRIC 金沢」の開業にあたり、スイートルームのアート作品を提案することになったのですが、「街の中心となり、一人ひとりの感性に合わせたその土地の旅を提案するホテル」というコンセプトをお聞きして、「この土地らしさ」を伝える作品として上出さんの「甘蕉」を提案させていただきました。「甘蕉」はこれまで吊るすタイプか置くタイプの2通りしかなかったのですが、上出さんと相談して壁面に飾る方法を編み出しました。この作品は遠くからは絵のように見えるけれど、近づいて見てみるとマークが絵付けになっていて、知っている人には「九谷焼なんだな」と分かってもらえる。宿泊客にはその見え方の変化を面白がっていただいたり、九谷焼という伝統工芸の産地であることを知ったりしていただけたのかなと思っています。

後半へつづく…